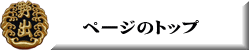| 1.枡合 |
| |
枡合 前正面 忠臣蔵
吉良邸討入り 大石内蔵助 義士の勇姿 |
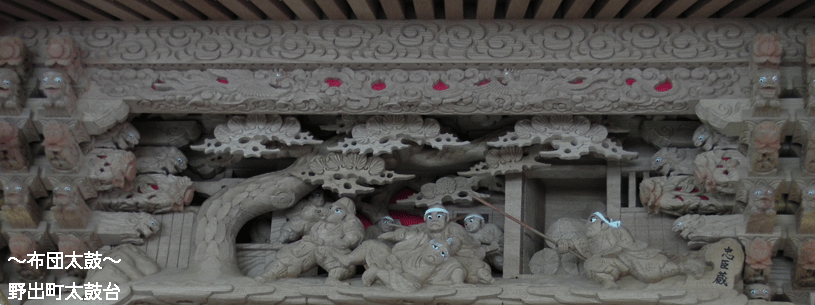 |
大石内蔵助等の赤穂浪士が吉良上野介を捕らえた場面の彫り物でございます。中央で倒れているのは吉良上野介であり、そして、それ以外 の人物は、火消し(火事)装束をした赤穂浪士になります。
実話
炭小屋(彫り物では右側の建物)前で吉良家の武士と一 悶着があった後、まだ、人の気配がするということで、炭小屋内部を探し、隠れていた上野介を間
十次郎によって発見され、十文字槍で刺され、その後、上野介の息子である左兵衛と居間で戦い を交えていた武林唯七が駆けつけ、大身槍でどどめを刺されました。ちなみに、左兵衛はというと、逃げたという説もあるのですが、額に傷つき血が目に入り気絶をしたという説の方が有力だと思われます。なぜ、唯七はとどめを刺さなかったというのは、炭小屋で上野介を発見したという知らせを受け、炭小屋へ向かったからです。ちなみに、唯七は、表部隊の屋内突入班を担当していました。
|
| |
枡合 右正面 忠臣蔵
堀部安兵衛と清水一学との奮戦 |
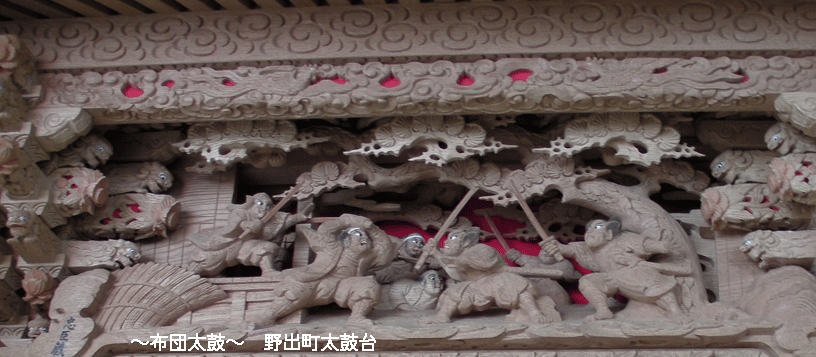 |
吉良邸北側の庭にて剣豪同士の戦い。中央左は、高田の馬場で名をあげた赤穂浪士の堀部安兵衛、中央右は吉良家側近の剣豪である清水一学であります。勝負は、堀部安兵衛が勝ちました。ちなみに、堀部安兵衛が担当していたのは、裏部隊の屋内突入班になります。
|
| |
枡合 左正面 忠臣蔵
勇士義士の活躍 |
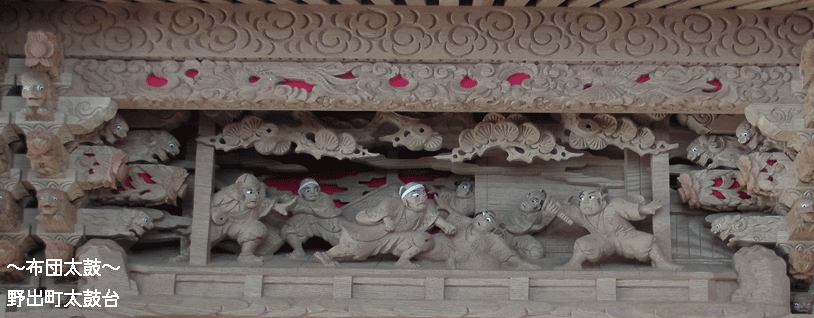 |
吉良邸で、吉良上野介を探しつつ、吉良邸の武士と戦っています。
|
| |
枡合 左正面 忠臣蔵
吉良邸討入り |
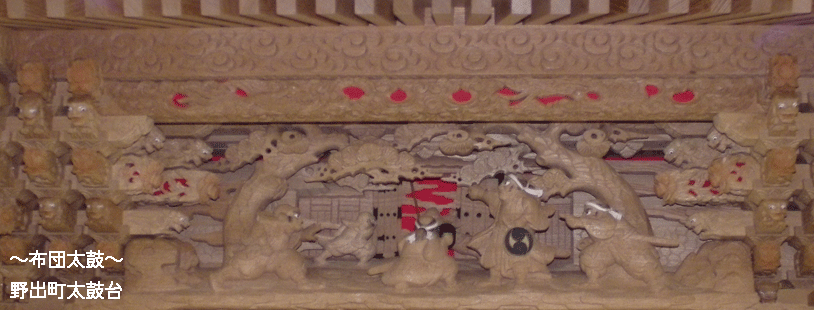 |
背景は、吉良邸討入が始まり、吉良邸表門から赤穂浪士がなだれ込んでいる場面になります。太鼓を持っているのは、大石内蔵助になります。裏門からは、主税らがなだれ込んでいます。
|
| |
| 2.虹梁 |
虹梁の彫り物は、仮名手本忠臣蔵が彫られています。この物語は、忠臣蔵を元に創作されたもので、登場人物の氏名は、別名となっています。虹梁 前正面の彫り物は、編集上、仮名手本忠臣蔵の人物名で編集をし、右正面、左正面、後正面については、忠臣蔵の実在の人物名で編集をしていますので、ご理解の上、御覧下さい。
|
| |
虹梁 前正面 仮名手本忠臣蔵
六段目 勘平切腹の場 |
 |
この場面は、早野勘平が切腹している場面になります。
山崎の小さな百姓、与一兵衛のあばら家は、早野勘平が身を寄せている場所で、女房のお軽、お軽の母親、そして、お軽の父、与一兵衛の三人で生活をしていました。
勘平は、四十七士としてもらうため、亡き殿の御石碑料を用意するための話です。そのため、与一兵衛は一文茶屋から100両を借りるため、50両は借りれたが、残り50両は娘を身売りすることで渡すという話になり、娘を引き渡すことになりました。その後、一文茶屋は、家に行き、お軽を駕籠に乗せるところに、勘平は家に帰ってきて、初めて妻を引き渡す事情を知り、生き別れとなってしまいました。
一文茶屋に行った与一兵衛は、まだ帰って来ず、後日、亡くなった与一兵衛が発見され、猟師仲間が家へ連れてきました。その姿を見て、母親は泣き崩れたが、勘平は驚かなかった。そこで、母親は、勘平がやったのではないかと疑い、勘平の懐中に手を入れて血の付いた財布を取り出しました。
その後、原郷右衛門と千崎弥五郎がやって来て、金を封したまま返しに来ました。そこで、母親はこのことを二人に言うと、郷右衛門からは「・・・田楽のように串刺しにしてやりたい・・・」、弥五郎からは「・・・亡き殿の恥辱になるのが分からないのか・・・」と言われ、たまりかねて勘平は小刀を腹に突き刺し、「・・・夕べ、与一兵衛殿にお目にかかった後、・・・二つの玉の鉄砲で撃ちとめ、手でさぐると、いのししではなく旅人でした。・・・懐中をさがしてみると、財布に入ったこの金がありました。・・・」という話になり、郷右衛門と弥五郎が、与一兵衛の亡骸の傷は、鉄砲の傷ではなく、刀でえぐった傷であることが分かり、勘平の疑いは晴れました。
郷右衛門は、懐中から連判状を出し、勘平は四十六人目として血判をして亡くなりました。
一番左は千崎弥五郎、左から2番目は早野勘平、左から3番目は原郷右衛門、一番右は、お軽の母だと思われます。
悲しい話ですね。
仮名手本忠臣蔵では、萱野三平重実は早野勘平、神埼与五郎則休は、千崎弥五郎、原惣右衛門元辰は原郷右衛門として語られています。
|
| |
虹梁 右正面 仮名手本忠臣蔵
九段目 山科閑居の場 |
 |
ここでは、大石内蔵助、主税と大石りく、子供達の別れについての場面が彫られています。左側の 場面は、妻子の旅立ちの準備、右の場面は妻子との別れの場面である思われます。大石内蔵助
は、赤穂城開城後は住まいを京の山科に移し、妻子とともに隠棲をしていました。妻子との別れの後、円山会議が開かれ、吉良邸討入決行を宣言し、内蔵助、主税とも山科を去り江戸へ向かって行きます。
仮名手本忠臣蔵では、大星由良之介、力弥等の名前で語られています。
|
| |
虹梁 左正面 仮名手本忠臣蔵
七段目 遊女お軽の悲哀(祇園一力茶屋の場) |
 |
祇園一力茶屋で、内蔵助が遊びに興じている場面が描かれています。浪士が来ても、酔った内蔵助は全く相手にせず、息子の主税から、瑶泉院からの密書を受け取ると、内蔵助の目つき急にが変わります。そこで、密書を読もうとしたところ、敵に寝返った大野九郎兵衛が声をかけてきます。九郎兵衛は、内蔵助の真意を探ろうとしても、内蔵助はかわします。その後、屋敷を抜け出します。
一番左側の人物、屋敷から出ていこうとする人物は内蔵助のように思えます。
実際は、祇園には「一力茶屋」は存在せず、「万屋」あるいは「万亭」であるとされています。では一力とはいうのは、「万」の文字を上下2つに分解して、一力としたそうです。しかし、内蔵助が実際よく通っていたところは、「井筒屋」だったらしいです。仮名手本忠臣蔵では、「井筒屋」より、「一力茶屋」のほうがふさわしいとして創作したそうです。
仮名手本忠臣蔵では、内蔵助、主税、九郎兵衛の3人は、大星由良之介、力弥、斧九郎兵衛の名前で語られています。
|
| |
虹梁 左正面 仮名手本忠臣蔵
十段目 義侠の商人 天川屋義平 |
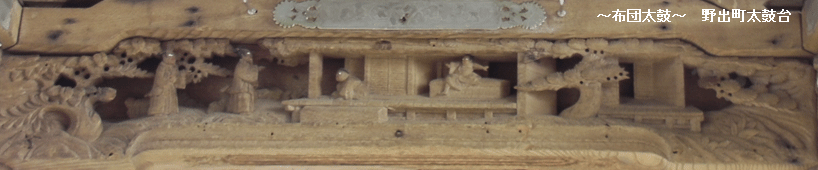 |
この場面は、吉良邸討入の武器調達をした天野屋利平(利兵衛)が、奉行所から長持を守っている場面です。左側にいる人物が奉行所の人であり、右側の長持(武器を入れる箱)の上に座っている人物は、まぎれもなく天野屋利平となります。天野屋利平といえば、”天野屋利平は男でござる”の名ゼリフは有名だと思います。
仮名手本忠臣蔵では、天野屋利平ではなく、天川屋義平で語られています。
|
| |