| 1.上側 |
| |

|
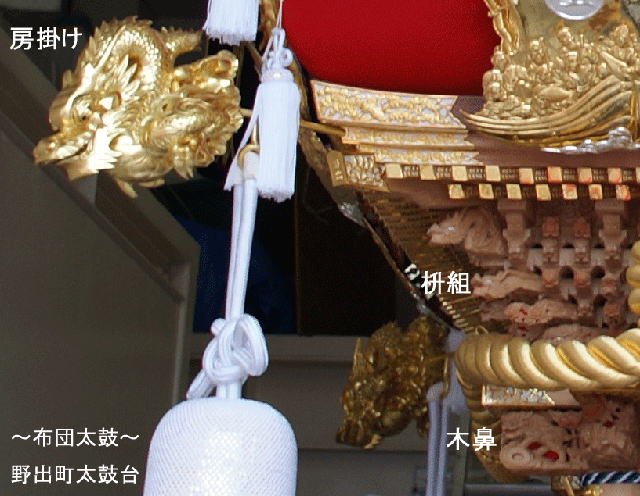
|
| |
| 2.四本柱 |
四本柱には四獣神の彫り物が彫られています。 |
| |
| 後左正面 |
後右正面 |
前左正面 |
前右正面 |
| 玄武 |
白虎 |
朱雀 |
青龍 |
 |
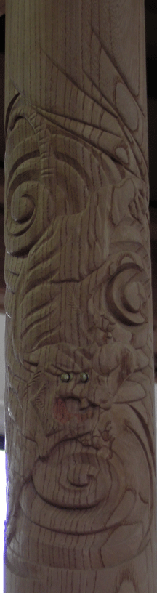 |
 |
 |
| |
| 3.匂欄 |
勾欄には富士の巻狩りの彫り物が彫られています。
1192年7月に征夷大将軍になった源頼朝は1193年3月・4月と、下野国那須野・信濃国三原等で巻狩りを行い、5月、富士の裾野に進みました。当時の武士にとっては、狩猟は単なるリクリエーションではなく、戦闘訓練・軍事演習そのものであり、神聖・重要な行事と意識されていた。
富士の狩場の準備は、北条時政、狩野宗茂(かのうむねしげ)に命じて、駿河・伊豆の御家人を率いて旅館以下の設営にあたったとされています。
頼朝は、12歳になる長男の頼家を伴って、5月8日から10日間以上、藍沢原、富士と愛鷹山(あしたかやま)の鞍部(あんぶ)をこえて西斜面で狩猟をされていたとされています。
下の彫り物は、こういった富士の裾野でされた狩猟の模様が彫られています。
これは、忠臣蔵と並んで有名なので触れておきたいと思います。狩も終わりに近づいた5月28日深夜、井出の館で曽我十郎時致(ときむね)・祐宗の曽我兄弟の仇討ちが発生しました。頼朝の寵臣(ちょうしん)、工藤祐経(すけつね)をかねてからの父の仇として復讐を遂げました。しかし、復讐を遂げた後、兄弟は討ち取られてしまいました。
|
| |
| 前正面 |
 |
| |
| 右正面 |
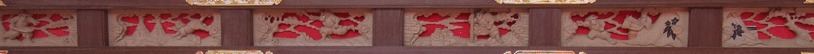 |
| |
| 左正面 |
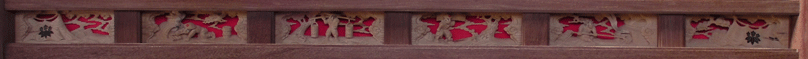 |
| |
| 後正面 |
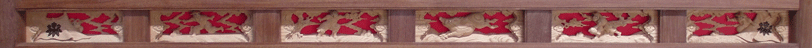 |
| |
| 4.縁葛 |
| |
| 前正面 桶狭間の合戦 |
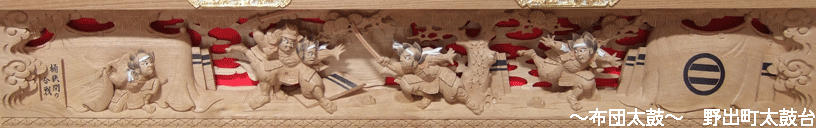 |
上の彫り物は、今川本陣で、信長本体と今川本体が戦っている場面が彫られています。
桶狭間の合戦が行われたのは、1560年5月19日午後2時前~午後3時頃。場所は、田楽狭間(でんがくはざま)でした。信長本体の兵士は2000人(全体で3000人)。今川本陣の兵士は5000人(全体で2万5000人)でした。この時、桶狭間だけでなく、同時に、数々の場所で織田家と今川家の合戦が行われてました。
5月19日午前2時、織田信長が居城である清洲城から数奇で熱田神宮へ向かいました。熱田神宮へ到着したのは、午前8時でした。午前9時頃に熱田神宮から丹下・禅照寺砦に向けて出発。その頃、兵士は2000人に増えていました。その頃早朝、今川方に2つの砦を落とされた知らせが信長に届きます。そのうち1つの砦を落としたのは、松平家康(当時
今川家家臣 徳川家康)でした。
午前10時頃、丹下・禅照寺砦に到着。その頃には、信長本体の兵士は3000人になっており、そのうち、1000人を砦に残し、今川本陣がある田楽狭間へ向かいました。午後1時頃、近くの太子ヶ山へ到着。その頃、雨が降っており、今川本陣は、酒盛りで浮かれていたのは有名だと思います。
ちなみに、田楽狭間に今川本陣があるのを見つけたのは、部下である梁田(さなだ)政綱の密偵でした。信長が、今川本陣の場所を探らせていました。
午後2時頃、雨が止み、信長本体は、今川本陣へ奇襲をかけました。午後2時半頃、今川義元は服部小平太や毛利新介に発見され、討たれることになりました。約1時間の合戦でした。この後、砦を落としていた松平元康は、大高城から岡崎城へ撤退をしました。
(注)時刻表記は、現在時刻の表記をしています、日付は、太陰暦で表記しています。
|
| |
| 右正面 秀吉本陣 佐久間の乱入 |
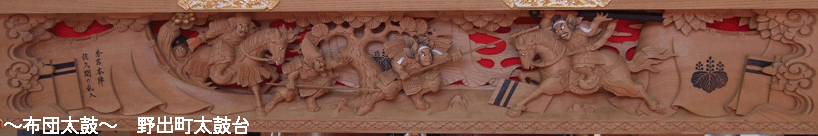 |
上の彫り物は、賤ヶ岳の合戦の局地戦、佐久間盛政が秀吉軍に攻めている場面が彫られています。
羽柴秀吉軍と柴田勝家軍との戦いになります。その時の勝家軍の先鋒が佐久間盛政でした。1583年3月12日、勝家軍が3万人、3月19日には秀吉軍は5万人でお互い賤ヶ岳で布陣をとっていました。この時、岐阜城の織田信孝が秀吉に対して反旗をひるがえしたため、秀吉の軍勢が岐阜城攻めに向かい、戦線を離れたことを好機とみた佐久間盛政が戦いを仕掛け、戦いの火蓋が切られることになりました。小競り合いは、もとより以前から続いていたものと思います。
4月20日午前2時、佐久間盛政軍(兵士約4000人)は、陣所であった行市山を出発して、大岩山砦(午前10時頃陥落)と岩崎山砦を陥落としました。その知らせを聞いていた秀吉は兵1万5000人を大垣から僅か5時間で木之本へ到着をしまし た。一部の書物では、「美濃大返し」とも書かれています。
賤ヶ岳付近で戦いが始まったのは、4月21日午前2時頃でした。
この後、福島正則(賤ヶ岳七本槍)らが、佐久間盛政が布陣する大岩山砦へ攻め入り、盛政が敗走することになり、前田利家隊の戦線離脱もあり、勝家軍全体が敗走することになりました。
後日、4月24日、夜明けとともに、勝家の居城、北ノ庄城を攻められ、午後4時頃、城に火がかけられ、勝家や家臣が切腹をすることにより、柴田家は滅びました。
(注)時刻表記は、現在時刻の表記をしています、日付は、太陰暦で表記しています。
|
| |
| 左正面 山崎の合戦 |
 |
上のの彫り物は、羽柴秀吉軍と明智光秀軍の戦いが彫られています。
後正面の話の続きとなります。興味のある方は、後正面から御覧下さい。
1582年6月12日、先方の高山右近隊(秀吉軍)は山崎まで進み、中川清秀隊(秀吉軍)は天王山を占拠していました。光秀軍の先陣も天王山の北麓および東麓を展開して、すでに小競り合いが起こっていました。この時の勢力は、秀吉軍4万人(本隊2万人)で、光秀軍1万6000人でした。
山崎の合戦が本格的に始まったのは、6月13日午後4時でした。天王山東麓を陣取っていた中川清秀・黒田孝高・神子田正治(みこだ まさはる)の隊に光秀軍が攻撃をしたのが開戦の合図となりました。乱戦の中、光秀が最も期待していた斉藤利三が討たれたことにより、御坊塚にいた光秀本隊が秀吉軍の攻撃を防げなくなり、勝龍寺城へ退却をしました。光秀は勝龍寺城で暗くなるまで待って、脱出して敗走したが、山科の小栗栖(おぐるす)で農民の出した竹槍によって殺害されました。
本能寺で信長を襲ってから11日目の出来事でした。
(注)時刻表記は、現在時刻の表記をしています、日付は、太陰暦で表記しています。
|
| |
| 後正面 尼崎の灘 |
 |
上の彫り物は、中国大返しの模様が彫られています。
この話は、1582年6月2日早朝に起こった本能寺の変から話が始まります。明智光秀の謀反(兵1万3000人)により、織田信長が本能寺で午前6時頃に切腹をされました。当時、備中高山城で毛利軍と戦っていました羽柴秀吉(のちに豊臣秀吉)に知らせが届いたのは、6月3日午前10時頃でした。毛利講和を成立させて停戦、4日の午前2時頃には、備前の国に秀吉は入り、6月8日午後10時頃、姫路城へ帰城しました。9日から2日間でへ入り、その後、12日には富田(茨木市)へ軍を進めました。
(注)時刻表記は、現在時刻の表記をしています、日付は、太陰暦で表記しています。
|
| |
| 5.下側 |
| |
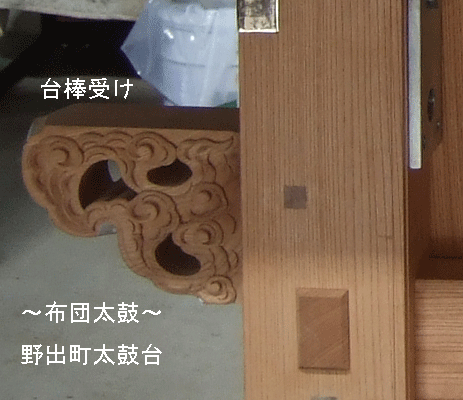
|

|
| |