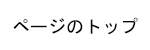| 1.春日神社 |
場所は、大阪府泉佐野市春日町にあり、奈良時代、坂上田村麻呂が、奈良県奈良市の春日大社の神を招き創建されました。天授二年(1376年)に坂上正澄によって社殿が建立されましたが、応永 の乱(1399年)の時に神殿の一部を残し焼失し、その後、天正13年(1585年)の羽柴秀吉による根来攻めの際に、再び焼失し、佐野村民(現 泉佐野市市街地)によって建立され、佐野の総社となりました。その後、明治39年8月に神社の併合・整理について指示があり、明治41~42年にかけて28の神社が春日神社に合祀されました。 ただ、全てがうまく合祀されたわけでなく、兵主神社(泉南郡南掃部村大字 西之内:現 岸和田市)のように取りやめになった神社もあります。合祀された神社は、下の一覧をご覧ください。
|
| 佐野村 春日神社に合祀した神社一覧 |
明治41年6月16日に合祀した神社
新道神社(字 新堂前)
小森神社(字 小森山)
大森神社(字 大森山)
牛神社(字 末広)
牛神社(字 時雨林庵)
佐野王子神社(字 今王子)
明治41年6月17日に合祀した神社
猿田彦神社(字 籠池)
日吉神社(字 井田)
熊野神社(字 元若宮)
牛神社(字 西出)
牛神社(字 加護池)
牛神社(字 妙光寺上)
|
明治42年5月28~31日に合祀した神社
今村神社(字 中西)
大引分神社(字 大引分)
射手弦神社(字 大門)
神引分神社(字 東千振)
中之宮神社(字 田出鼻)
椋山神社(字 椋山)
西出神社(字 西出)
住吉神社(字 坂口)
西村神社(字 車町)
沖津(沖州)神社(字 土山)
浜出神社(字 浜出)
八坂(祇園)神社(字 祇園)
松崎神社(字 松崎)
若宮神社(字 高松)
水分神社(字 籠池)
稲荷神社(東鳥取村:現 阪南市)
|
| 2.春日神社御祭神 |
春日神社(中央本殿)
建甕槌命(タケミカヅチノカミ) 春日四座
齋主命(イワイヌシノミコト) 春日四座
姫大御神(ヒメオオミカミ) 春日四座
天児屋根命(アメノコヤネノミコト) 春日四座
天押雲根命(アメノオシクモネノミコト) 若宮明神
濱出神社(左本殿)
事代主命(コトシロヌシノミコト)
猿田彦命(サルタヒコノミコト)
建角見命(タケツヌミノミコト)
大山祇命(オオヤマツミノミコト)
住吉神社(右本殿)
底筒男命(ソコツツオノミコト)
中筒男命(ナカツツノノミコト)
表筒男命(ウワツツオノミコト)
素戔嗚尊(スサノオノミコト)
神功皇后(ジングウコウゴウ)
応神天皇(オウジンテンノウ)
菅原道真(スガワラノミチザネ)
赤手拭稲荷神社(境内社)
大山祇命(オオヤマツミノミコト)
倉稲魂命(ウガノミタマノミコト)
|
| 3.住吉神社 |
当時、上善寺(現 栄町)内に住吉神社があり、明治元年の神仏分離令が施行され合祀されることとなりました。明治42年、春日神社に合祀される前は、住吉神社の例祭として太鼓台が運行されていました。
例祭考察においても触れております。
|