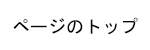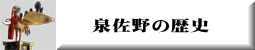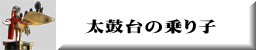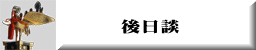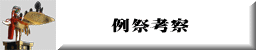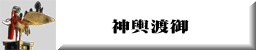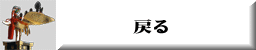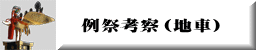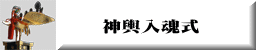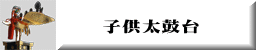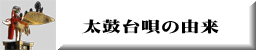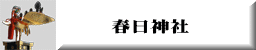| ここでは、尻取り唄に触れておきたいと思います。 |
| 「尻取り」の意味は、ご存知だとは思うのですが、こう紹介されています。 一句の最後に音を次の句の音に言い掛けつつ前後の連絡もない文章をつくる遊び。 西沢一鳳(嘉永五年没)の「皇都午睡」初篇上に「尻付 跡尻」と題して下記のように紹介されています。 又江戸にては尻取廻しと云ひ、京摂にては跡付と云ふなり。 句の下の詩を次の句の上に置くことなり。 江戸、(上略)六じゃの口をのがれたる、たるは道連れ世は情、 なさけの四郎高方、つなでかく繩十文字(下略)、 上方、稲荷の鳥居に猿の尻、のしりのしりと上下で、 下の関までおーせっせ、お関が弟は長吉で、 長吉長吉あばゞにつむりてんてん、天々天満の裸巫女、 みこか戻ろか住吉参り、参り下向の足休め、 すめの判官盛久は、久松そこにか冷たかろ、 たかろは船頭の松右衛門、ゑもん繕ひ正座する、 浅間に富士の山(下略)などなり ということで、百年前にはすでにこの遊びが江戸・上方ともに流行していたことが分かります。 |
| 次の「尻取り唄」は、明治時代に大阪でうたいはやされていたものです。 近江の石山の秋の月、月に村雲花に風、 風の便りに田舎から、唐をかくせし淡路島、 縞の財布に四,五十両、十郎五郎は曾我のこと、 らいし(雷子)は嵐の三五郎で、ゴロゴロ鳴るのは雷で、 エーヤホーヤ、エアサッサ、 稲荷の鳥居に猿の尻、尻と尻との押合ひで、 エーヤホーヤ、エアサッサ。 牡丹に唐獅子竹に虎、虎追うて走るは和唐内、 わとないお方に知恵貸そか、知恵の中山清閑寺、 清閑寺の和尚さん坊さんで、坊さん蛸食てへどついた、 (このあとへ「その手でお釈迦さんの顔撫でた、お釈迦さんはびっくりして飛んで出た」と 続けることがある。) エーヤホーヤ、エアサッサ。 (また、清閑寺以下を 「清閑寺の和尚さん坊さんで、坊さん蛸さん入道さん、 玉子のふわふわあがりんか、今日は精進もったいない」 とつづける。この方が旧体) 太鼓台の囃子(唄)は、上記の「尻取り唄」が由来になっていると思われます。 |