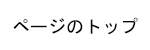| 1.はじめに |
春日神社の祭礼は、佐野太鼓台祭り以外にも、結陳祭や地車(だんじり)祭等も執り行われ佐野界隈の祭礼として賑わっておりました。その2つの例祭に触れたいと思います。
|
| 2.結陳祭 |
1月11日に執り行われていた例祭は、「結陳祭」です。その「結陳祭」というのは、17歳以上の男子が社頭で射弓を行い、競馬を行うものであり、この華やかな有様を、「あすは春日のけんちの祭り佐野の女衆の衣裳くらべ」とうたわれたそうです。ただ、明治25年に、「結陳祭」が中止となりました。
|
| 3.地車祭 |
地車祭は10月11日に執り行われていました。明治41年10月11日の「地車曳出願」が、佐野警察分署長の許可を得ていたという記述が残っています。後に10月10日、11日に例祭が執り行われています。現在は、地車は存在せず、祭礼は執り行われておりません。
|
| <1>角鼻町の地車 |
角鼻町の地車は、昭和10年、佐野町制25周年を祝い、曳行されている写真にて確認しています。昭和19年には、曳行はされておられないのですが、角鼻町の地車存在が確認出来ております。昭和24年4月1日に区画整理が行われており、その際、角鼻町は消滅し
て栄町や本町に編入されました。その後、地車の存在は確認出来ておりません。
|
| <2>大西町の地車 |
大西町の地車は、本の写真と記述、映像で確認をしました。
当時、大西町の中心は二惣分町内会で、運営していたのは二惣分青年団でした。二惣分とは、三本松町・大西町・高松町(現大西町と西本町)をさします。昭和14年、岸和田市大手町から売りに出されていた地車を湊と競合していました。青年団役員は、湊の先手を打って購入交渉をしていたのですが、町内会が反対したため、購入をあきらめることになりました。
しかし、その直後、岸和田市福田町のだんじりが売りに出す話があり、青年団役員が福田町と購入の交渉し、合意に至り購入することになりました。当時のだんじり祭りの例祭日は統一されてなく、福田町の秋祭りが終わってから、佐野の秋祭りが執り行われていました。福田町の秋祭りの終わる日、西惣分は、地車を福田町から小栗街道を通り、曳行して佐野まで持ち帰ったそうです。
その後、昭和24年4月1日に区画整理があり三本松町・大西町・高松町の3町は、大西町と西本町の2町となりました。その区画整理が影響して、地車は曳かれなくなり、昭和37年中庄に売却されました。また、当時の地車小屋と町会館は、孝子越街道沿いにあったといわれています。
|
| <3>湊の地車 |
湊の地車は、春日神社の祭礼ではないのですが触れておきたいと思います。
祭礼日は、10月7日、8日の両日でであり、奈加美神社の例祭(?)ではなかったかと思われます。根拠は春日神社と例祭日が違い、昔、湊村は、中庄村と合併していて、中庄村であったからです。
当時、大きな地車と小さい地車の2台ありました。昭和14年、岸和田市大手町から地車(大きな地車)を購入し、大手町から佐野まで地車を曳行して持ち帰ったそうです。当時の地車の曳行コースは、春日神社(現 春日町)の前を通り、春日通りを通り、大西町の境まで来ると、方向転換して帰るのがコースになっていました。
後に、小さい地車は、昭和21年に東大阪市の中野に売却され、大きな地車は、昭和39年に奈加美神社(現 中庄)に寄贈されています。大きな地車は、帳舎に入らなかったため、雨ざらしのまま表に置かれていました。それを見た貝塚の馬場の人に大きな地車を売却をしました。
|
| <4>その他 |
昭和10年に佐野町制25周年を祝っている高松町(現 大西町)の屋台(山車)、昭和24年4月1日に区画整理後に誕生した、栄町の屋台(山車)を本の写真にて確認をしました。
|