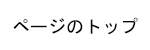| 1.佐野太鼓台祭り |
佐野太鼓台祭りは、いつから執り行われるようになったかは年代は不詳です。また、太鼓台として伝わったのか、様々な諸説があります。
私が間接的に知り得ていることは、新居浜から佐野に太鼓台が伝わった説です。それは、昔、太鼓台同士が棒鼻に乗せる行為、現在、新居浜でもされている似た行為が行われていたことを史実で確認しているからです。
現在、四国の方では、担ぎ棒(横棒)が無い状態が主流ですが、昔は、横棒が取付けてあったと言われているようです。現在も横棒を取付けている地区が存在し、混在している地区もあるようです。
淡路島から伝わった説もあります。
自由都市であった堺から伝わった説もあります。九州の太鼓台は堺壇尻として伝わった説。
また、個別に執り行われた祭りに、布団が取付けられる文化が伝わった説。
佐野から各地へ伝わった説です。先代は、地車屋根の太鼓台もしくは担い地車によく似たものである話もあります。佐野の豪商、食野家や唐金家が強力であった時代でした。
海岸へ流れ着いた廃材等を使用して太鼓台を制作したという逸話もあります。この話は、本当の逸話だと思われます。
さて、当時、天保年間に残されている古文書には次のようなことが書かれています。私の手書きですので、御了承お願いします。
|
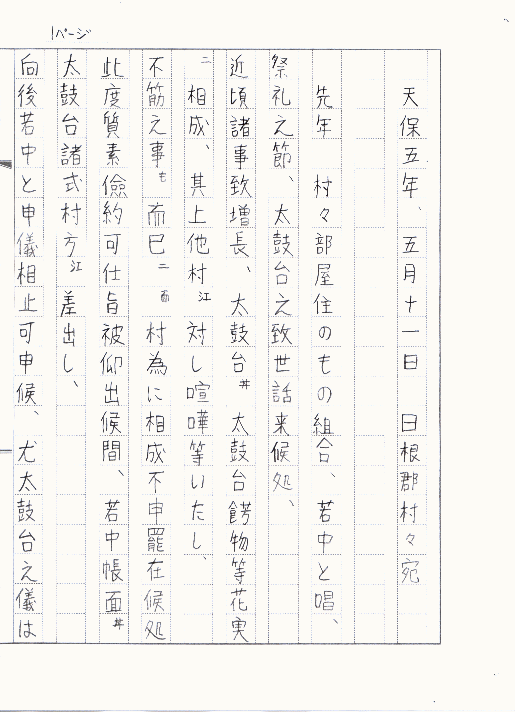
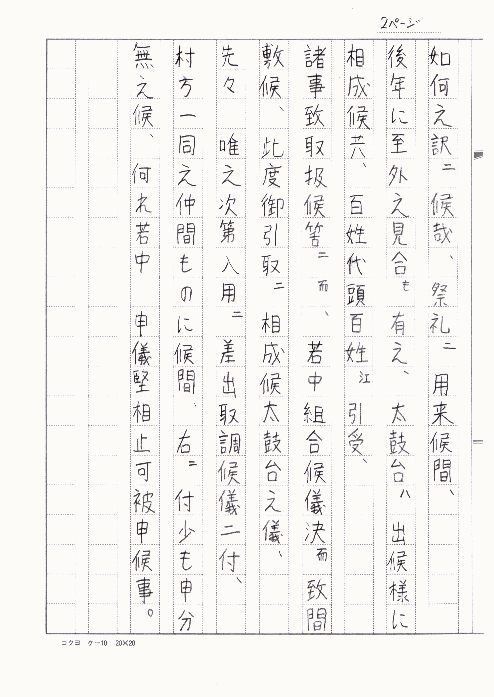
手書きにて掲載
|
| 2.佐野太鼓台祭り |
ここでは、明治42年に春日神社へ合祀される前の佐野太鼓台祭りは、春日神社の例祭であったのか、それとも、被合祀神社の例祭であったのかという真実に迫りたいと思います。
「明治初期の神輿渡御と太鼓台・壇尻」という論文を引用させて頂いています。
①春日神社夏の例祭には神輿だけが渡御していた。
②春日神社の神輿は佐野全町を回っており、これは同社がもともと佐野の惣社的意味合いをもって
いたからだと考えられる。
③他方、住吉神社の夏の例祭には、神輿と太鼓台の渡御がおこなわれていた。
④住吉神社の太鼓台を出すのは、野出町、円田町(現 春日町の一部)、新町という漁師の住む浜
方3ヶ町で、これは現在春日神社の出す町と同じである。
⑤これに加えて住吉神社の例祭では、当時「水揚」と呼ばれた浜沖士(沖仲士)の集団が太鼓台を出
した。彼らは、沖合いに停泊する船と浜にある倉庫との港湾荷役に携わっていた人々であった。
⑥当時、佐野内の神社の祭りで神輿の渡御があったのは、春日神社と住吉神社の2社のみだった。
⑦明治13年、もともと1ヶ月以上離れていた両社の祭日が一続きになり、春日神社祭礼(夏祭り)に
も太鼓台が出されるようになった。春日神社の例祭日が7月24日、住吉神社の例祭日が7月25日。
⑧春日神社を含む佐野内にあった各村社では秋祭りが行われ、町内からだんじりが曳きだされていた
(住吉神社は村社ではない)。
⑨村社では雨乞い儀礼も行われたがだんじりはその際にも曳きだされた。
⑩こうしたことから明らかのように、住吉神社は海に関わる人々の祭りであり、太鼓台の運行も彼らに
よって支えられていた。一方、村社の祭りやだんじりは、雨乞いから結びついていることからもわかる
ように陸(おか)方の農民と結びついた祭りであった。
まとめると
春日神社=佐野全体のの惣社的性格=陸方(農民)の祭り=だんじり運行
住吉神社=特定小地域の氏神(海神)=浜方(漁師・沖仲士)のまつり=太鼓台運行
|
| 3.神輿担出願(明治41年) |
明治41年7月24日の’神輿担出願’、同じく、明治41年7月24,25日の’太鼓台担出願’が、佐野警察分署に提出し、運行の許可をもらっています。また、神輿渡御について書かれた記述があるのですが、それを紹介したいと思います。
神輿担出願
「明治四十一年七月二十四日氏神祭典ニ付、神輿担出致度候間、御許可相成度願上候也」とし、
「時間、午前一時ヨリ午後五時迄」と、世話人十五人連名で、(佐野)村長宛に提出した。
その後、別に「道筋書」「請書」を添付して佐野警察分署に提出し、運行の許可をもらっています。「道筋書」の記述は、次の内容です。
「道筋書」(明治41年の神輿渡御)
春日神社ヲ出テ大西町ニ至り、停車場ニ引返シ、角鼻町、車町、円田町ヲ経テ新町ニ至り、海浜ヲ
野出町ニ出テ同所ヲ孝子街道筋ヲ北、春日神社ヘ帰着ス
注)角鼻町は現在の本町、車町と円田町は現在の春日町であります。
|
| 4.春日神社合祀後(明治42年~昭和18年) |
明治42年、住吉神社が春日神社へ合祀後、例祭日が7月24日に統一され、両祭礼を合体し、1つの神輿が住吉神社、春日神社の御旅所を巡行するようになり、春日神社の例祭となりました。
大正10年頃、一年限りですが小路出町(現 本町)にも、太鼓台が存在していたという記述が残っています。沖仲士太鼓台のことだと思われます。記述の上から、毎年太鼓台を運行しているわけではなかったということと受け取れます。
その太鼓台は、よそから中古で購入し、大きさは新町より一回り小さかったようです。一年限りになってしまったのは、担ぎ手が集まらないというのが理由だったそうです。
昭和10年代に入ると、沖仲士の人たちは、国へ帰ったり、戦争へ行ったりして、小路出町(現 本町)で活躍していた沖仲士太鼓台の運行中止となりました。
|
| 5.佐野太鼓台祭り(昭和19年) |
7月23日、24日には佐野町春日神社の夏祭りであるが、太鼓台は出なかった。
7月24日には、午前10時から春日神社にて幣帛供進の式典があり、供進使には古妻町長がなって吏員1名を供として、参向の儀式を行い、之には近村の神官十数名、国民学校生徒数十数名、参列して拝殿において壮厳に行われた。
太鼓台が出ないので、昼間は境域外鳥居前に露店3,4軒あるだけであったが、夜には境内にのも3,4軒出ていた。どの店も、玩具類の店だけであった。神社付近のアイスケーキ屋でケーキを売っていて、一本2銭であるが、営業用の砂糖の配給もないので、甘みが少しもしないケーキであった。
|
| 6.佐野太鼓台祭り(昭和20年~昭和64年) |
昭和20年代に入ると、新町は人手が足りなく、現在の太鼓台を担ぐのは無理と思い、沖仲士の太鼓台を借り、1,2年担ぐが、宮入りの最中に四本柱が折れて、現在の太鼓台を担ぐようになります。その後、沖中士の太鼓台の四本柱を修理し、昭和30年代に新町が本町(当時、ほんまちではなくもとまちと読んだ)へ手渡し、本町がその太鼓台を1,2年(昭和38年頃)担いだ後、中止したと言われます。中止した後、沖仲士太鼓台を分解して燃やし運行中止となりました。聞いた話・資料の内容でもありますが、文責は当webサイト管理者の私が持ちます。
当時の沖仲士太鼓台の布団は紫でした。昭和戦前には、土呂台に左右前後に4人が肩を入れ担いだ、4人で舞い舞いをした、春日神社から佐野駅(現 泉佐野駅)まで担いで走ったという逸話があります。今では、考えられないことを行っていたようです。
当時の野出町御旅所は、野出町の砂浜にありました。神輿を担いだまま海に入っていっていたものです。当時の町会館の場所は、野出町は野出町本通り沿い、大正年間に建てられた会館でした。春日町は春日公園すぐ横、新町は現在の長生会館でした。当時の青空市場は、臨海線山側にあって現在も名残が残っています。当時の賑わいは凄いものでした。
子供の頃はその付近に沢山置いてあったリヤカーに乗って遊んだ覚えがあります。当時の泉佐野漁港は、現在の臨海線の場所になります。現在の青空市場近くに、当時、防波堤があり沖には灯台がありました。また、釣り客もいた記憶があります。当時の野出町太鼓台倉庫は、現在の野出町会館の位置にありました。
野出町太鼓台の装飾も、現在のように紋(町紋)はなく、布団屋根の前後に旭日旗を取り付けていました。そのうえで野出町は青年団旗を布団屋根に掛けていました。また、現在より荒々しい雰囲気が出ていました。
|
| 7.佐野太鼓台祭り(平成元年~平成21年) |
昭和62年より関西空港、りんくうタウン建設。平成2年、野出町の神輿渡御(神輿番)を最後に野出町御旅所(野出浜)での海岸(海に入る)の神輿担ぎ中止。当時の防波堤(堤防)は現在は一部記念で残るのみ。
りんくうタウン完成により、当時の泉佐野漁港、防波堤のあった場所へ各町会館、そして太鼓台倉庫移転。一部の御旅所や休憩所が移設される。
平成12年度より3ヶ所に献灯台設置。後述で紹介しています。
平成14年度
野出町と春日町の2町による担ぎ合い。時間は5分。
位置は、野出町(内原店前)、春日町(内原店山側)。
平成15年度
例祭日も7月23、24日から、7月の海の日が絡む日・月に変更。
駅前通り商店街(堺阪南線海側)にて3町の担ぎ合い開始。
宵宮は午後7時30分~午後7時50分。
本宮は午後8時10分~午後8時30分。
平成17年度まで神輿当番の町は、本宮夜の運行は泉佐野駅には行けず、りそな銀行、UFJの交差点付近までしか太鼓台運行が出来ませんでした。
平成18年度、青年団三町連合会発足。3町の担き合いは、宵宮は土丸栄線(南海本線~堺阪南線間)で行なわれるようになりました。午後7時~午後7時30分。本宮は駅前通り商店街。午後8時10分~午後8時30分。
一部の交通規制を通行注意から通行止へ強化。
平成19年。
若頭会にも三町連合会発足。
7月7日、午後8時より青空市場で試験担ぎ。駐車場2周。5分間担ぎ合い。
宵宮・本宮の両日午後6時40分~午後7時50分まで、土丸栄線 南海本線海側~栄町交差点まで通行止。
3町の担き合いは両日、土丸栄線へ変更。時間は午後7時20分~午後7時40分。
本宮の宮入開始時間変更。午後1時→正午。
平成20年。
3町の担き合いの時間。宵宮は午後7時20分~午後8時。本宮は午後7時40分~午後8時10分。
平成21年。
今年度から、女御輿参加、7月5日(日)入魂式。
7月11日試験担ぎ、午後7時10分~午後7時40分。
宮入が、各3町子供太鼓台、女御輿、各3町太鼓台と一続きとなる。
各3町子供太鼓台宮入。午前10時20分~午前11時25分。
女御輿。午前11時35分~午前11時50分。
各3町太鼓台宮入。正午~午後13時50分。
以上、運行時間は、平成21年度太鼓台運行表を抜粋。
野出町太鼓台。7月19日(宵宮)昼運行のみ。最初で最後。
太鼓台布団上部にプラカード設置。
新地通り商店街運行中、プラカードが電線にあたる為取り外し。
野出町太鼓台。7月20日(本宮)のみ。最初で最後。
旧海岸通りで太鼓台を担ぐ(野出町墓地半ば~野出町会館)。
その後、野出町御旅所にて。
打ち上げ花火を上げながら、太鼓台を担ぐ。
青年団、若仲会を中心とする舞い舞いを披露。
最後、野出町会長、野出町総指揮、青年団団長(胴上げ)、若仲会会長、若頭会会長
(現・・委員会会長)による挨拶。
|
| 8.野出町太鼓台昇魂式 |
平成21年12月6日 野出町太鼓台昇魂式。
午前10時30分前 新調委員会会長、青年団団長の挨拶。
午前10時30分 野出町会館出発。
コマをつけたまま春日神社へ向かう。
午前11時30分 春日神社到着
横棒を取り付け、コマを外す。
午後12時30分~午後1時迄 春日神社境内で担ぐ。
途中、舞い舞いをする。
午後1時~ 昇魂式式典(神事)
拝殿に関係者役員が入り、式典(神事)始まる。
式典終了後、境内でコマを取り付け、横棒を外して野出町会館へ帰る。
午後3時頃~ 会館内で太鼓台を担ぐ(担ぎ収め)。
時間20分位。
その後、前町会長の挨拶、そして、町会長による乾杯の音頭。
午後5時過ぎ迄 会館で野出町の皆さんと打ち上げ。
野出町太鼓台。110年間、お疲れさん。そして、思い出ありがとう!
|
| 9.野出町太鼓台新調 |
平成22年5月15日 入魂式(予定)
午前8時 板谷工務店出発
午前9時 春日神社着
午前11時 入魂式
午後0時30分 春日神社出発
午後1時30分 野出町会館着
午後2時~4時 バーベキュー
午後4時~ 片付け
午後5時 解散
平成22年5月23日 お披露目式(予定)
午前8時 式典
午前8時30分 鏡割り
午前9時 野出町会館出発
午前10時 春日神社着
午前11時 春日神社出発
正午 野出町会館着
午後1時~4時 宴会
午後4時~ 片付け
午後5時 解散
|
| 10.佐野四町祭り(平成22年~令和元年) |
平成22年7月10日 青年会議所(JC)イベント参加
場所 りんくう公園
午後3時30分前、太鼓橋手前遊歩道に配置。
午後3時30分~午後4時30分 3町が担ぐ(20分×2セット)
注) 以上は、運行時間表を確認にて明記。
平成22年度の試験担ぎはイベント参加により中止。
平成22年7月18日(宵宮)
午後0時40分過ぎから10分間、つばさ通り商店街にて担ぎ合い。
午後2時30分から三町とも一斉休憩。
三町とも担ぎ棒の結び方を統一する(当時の所要時間は1時間以上)。
平成23年7月16日(土) 試験担ぎ
本祭り一週間前から前日に変更。
試験担ぎ後、親睦会。
平成23年7月17日(宵宮)
午後1時15分頃から、つばさ通り商店街にて担ぎ合い。
午後1時30分から三町とも一斉休憩。
※つばさ通り商店街にての担ぎ合いは平成22年、23年の2年間のみ。
平成24年7月8日(日) 試験担ぎ
本祭り一週間前に変更。
場所 青空市場近く
試験担ぎ時間 午後1時~午後3時
親睦会 午後3時~午後5時
平成24年7月15日(宵宮)
午後1時30分から午後3時30分まで、4町によるパレード開始。
パレード開始場所は、内原前。
パレードは駅前通り商店街(堺阪南線海側)。
各町一町で持ち時間を担ぐ。
その後、四町担ぎ合い(四町揃って)。
場所は、駅前通り商店街(堺阪南線海側)。
午後4時頃四町休憩。
平成24年7月15・16日(宵宮・本宮)
四町担ぎ合い
昨年までは、女神輿が担いだ後、三町で担ぎ合い。
今年は、四町揃っての担ぎ合い。
平成25年7月14・15日(宵宮・本宮)
午後7時~午後8時。
よさこい
よさこいと女神輿のコラボ
三町担ぎ合い
平成26年度から 春日町子供太鼓台は運行しておりません。
平成26年7月12日(土) 試験担ぎ
午後1時半~午後3時30分(定刻時間)
駅前通り商店街・つばさ通り商店街
平成27年7月12日(日) 試験担ぎ
午後1時~午後3時30分(定刻時間)
つばさ通り商店街のみに変更。
平成27年 かきあい
よさこい
よさこいと女神輿のコラボについては、本宮(20日)のみに変更。
三町担ぎ合い
注)時間については、公式時間であり実際の時間ではありません。
平成28年7月3日(日)
神輿大修理(植山工務店)による入魂式 入魂式 8時30分~
試験担ぎ 午後1時30分~午後3時30分
駅前通り商店街・つばさ通り商店街
平成28年7月17・18日(日・祝) かきあい
和太鼓
女神輿
三町担ぎ合い
平成29年7月16日(宵宮)
野出町太鼓台 ライトアップ使用。
令和元年
野出町太鼓台 宵宮・本宮 両日 ライトアップ使用。
和太鼓は本宮のみ。
|
| 11.佐野四町祭り(令和2年~) |
令和2年
東京オリンピック開催により海の日変更になるも、新型コロナウイルスの影響によりオリンピック延期。
祭礼日 9月19日(土)・20(日)に変更。新型コロナウイルスの影響により祭礼中止。
令和3年
祭礼日 9月18日(土)・19(日)。新型コロナウイルスの影響により祭礼中止。
令和4年
各町太鼓台修理。
新型コロナウイルスの影響により野出町、新町の2町にて祭礼。
子供会は不参加。
試験担ぎ 9月11日(日)。
祭礼日 9月17日(土)・18(日)。
野出町、新町の2町にて かきあい。
野出町、新町ともに両日ライトアップ使用。
献灯台 泉佐野駅前(海側)。
令和5年
野出町 宵宮 ライトアップ、本宮 提灯
新町 以降両日ともライトアップ使用。
春日町 これまで通り提灯を使用。
子供会 野出町のみ運行
令和6年
祭礼日 5月18日・19日に変更。
取締まりにより、安全運営・運行予定時間厳守。
試験担ぎ 女神輿は関係者のみで参加。
春日神社宮入
女神輿 午前11時~午前11時25分。
宮一番 午前11:30分~正午。
宮二番 正午~午後0時30分。
宮三番 午後0時30分~午後1時。
野出町太鼓台 宵宮 ライトアップ、本宮 提灯。
3町の子供太鼓台 運行休止。
|